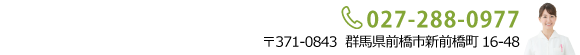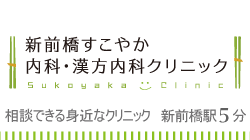2026/2/5
🌸節分が過ぎたら「春の養生」へ
― 立春から始める漢方的体調管理 ―
節分が過ぎ、暦の上では「立春」を迎えました。
まだ寒さは残っていますが、漢方ではこの時期を「冬から春へ、体が切り替わる大切なタイミング」と考えます。
実は、毎年この時期に「なんとなく体がだるい」「気分が落ち着かない」「胃腸の調子が悪い」といったご相談が増えてきます。
それは決して気のせいではなく、季節の変化に体が順応しようとしているサインなのです。
🌱漢方で考える「立春」の体の変化
漢方医学では、春は「肝(かん)」の季節。
肝は、自律神経・感情・血流の調整に深く関わる臓です。
立春以降は、冬にため込んだエネルギーが動き始める、気(エネルギー)が上にのぼりやすくなる、自律神経が不安定になりやすい、といった変化が起こります。
その結果、イライラしやすい、眠りが浅い、頭痛・肩こり、食欲不振や胃の不調といった症状が出やすくなるのです。
🌿節分後に起こりやすい不調
この時期に多いお悩みには、次のようなものがあります。
「春先のだるさ、疲れやすさ」
「気分の落ち込み、不安感」
「頭痛、めまい、肩こり」
「胃もたれ、食欲不振」
「花粉症の初期症状」
これらは「病気」というより、季節と体のズレによるものが多く、漢方治療が得意とする分野です。
💊立春以降によく使われる漢方薬(保険診療)
体質や症状に応じて、次のような漢方薬が用いられます。
加味逍遙散(かみしょうようさん)
― 立春から始める漢方的体調管理 ―
節分が過ぎ、暦の上では「立春」を迎えました。
まだ寒さは残っていますが、漢方ではこの時期を「冬から春へ、体が切り替わる大切なタイミング」と考えます。
実は、毎年この時期に「なんとなく体がだるい」「気分が落ち着かない」「胃腸の調子が悪い」といったご相談が増えてきます。
それは決して気のせいではなく、季節の変化に体が順応しようとしているサインなのです。
🌱漢方で考える「立春」の体の変化
漢方医学では、春は「肝(かん)」の季節。
肝は、自律神経・感情・血流の調整に深く関わる臓です。
立春以降は、冬にため込んだエネルギーが動き始める、気(エネルギー)が上にのぼりやすくなる、自律神経が不安定になりやすい、といった変化が起こります。
その結果、イライラしやすい、眠りが浅い、頭痛・肩こり、食欲不振や胃の不調といった症状が出やすくなるのです。
🌿節分後に起こりやすい不調
この時期に多いお悩みには、次のようなものがあります。
「春先のだるさ、疲れやすさ」
「気分の落ち込み、不安感」
「頭痛、めまい、肩こり」
「胃もたれ、食欲不振」
「花粉症の初期症状」
これらは「病気」というより、季節と体のズレによるものが多く、漢方治療が得意とする分野です。
💊立春以降によく使われる漢方薬(保険診療)
体質や症状に応じて、次のような漢方薬が用いられます。
加味逍遙散(かみしょうようさん)
…気分の不安定、イライラ、不眠がある方に。「肝」の異常は「血」の異常に現れます。加味逍遙散は、交感神経の昂ぶりを制御しつつ、血の異常による諸症状の改善に有効なバランスの良い方剤です。女性にしか使用できない薬ではありません。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
…喉のつかえ感、不安感がある方に。半夏厚朴湯の本来の目的は、気の流れが停滞したことで生じる「痰」という病的産物を取り除くことです。気が動こうとしている春の時期には、痰を除去して気の流れをスムーズにすることが大切です。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
…春先に疲れやすく、風邪をひきやすい方に。何かと出番が多く、使い勝手の良い漢方薬です。胃腸を元気にして気の生成を高め、その気を肺に持ち上げて全身へと供給することで疲労感を軽減します。免疫力を高める効果もあるので、風邪の予防にもよく使用されます。
いずれも体質に合わせて選ぶことが大切ですので、自己判断ではなく医師にご相談ください。
🍽️春に向けた食養生のポイント
立春以降は、「ため込む」よりも「巡らせる」ことが大切です。以下のポイントに注意して、胃腸をいたわることが春の体調安定につながります。
いずれも体質に合わせて選ぶことが大切ですので、自己判断ではなく医師にご相談ください。
🍽️春に向けた食養生のポイント
立春以降は、「ため込む」よりも「巡らせる」ことが大切です。以下のポイントに注意して、胃腸をいたわることが春の体調安定につながります。
【食養生のポイント】
①脂っこいもの・甘いものを控えめに
②ほうれん草、菜の花、春菊などの青菜を取り入れる
③冷たい飲み物は控え、常温〜温かいものを
①脂っこいもの・甘いものを控えめに
②ほうれん草、菜の花、春菊などの青菜を取り入れる
③冷たい飲み物は控え、常温〜温かいものを
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メンバー募集中です☆
YouTube ▶ https://www.youtube.com/channel/UCZ77mmHqYxWycSWBzpDRsxQ
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
#漢方 #新前橋 #群馬 #前橋 #高崎 #がん免疫 #がん免疫療法 #プラセンタ #高濃度ビタミンC #しらたま点滴 #にんにく点滴 #NMN #幹細胞
📍Googleマップで「前橋市 漢方内科」と検索していただくと、アクセス・診療時間をご確認いただけます。
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メンバー募集中です☆
YouTube ▶ https://www.youtube.com/channel/UCZ77mmHqYxWycSWBzpDRsxQ
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
#漢方 #新前橋 #群馬 #前橋 #高崎 #がん免疫 #がん免疫療法 #プラセンタ #高濃度ビタミンC #しらたま点滴 #にんにく点滴 #NMN #幹細胞
📍Googleマップで「前橋市 漢方内科」と検索していただくと、アクセス・診療時間をご確認いただけます。