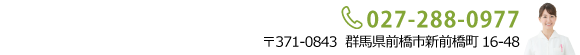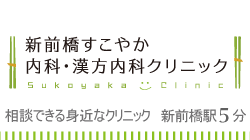桜にまつわる漢方薬⁉
2025/4/10日本各地で桜が満開となっています。
今回は桜にまつわる漢方薬の話をご紹介いたします。
「十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)」という漢方薬があります。
炎症を伴う皮膚疾患であれば何にでも使用できるくらいバランスが良い漢方薬です。
この漢方薬は、出典の違いから桜皮(おうひ=ヤマザクラの樹皮)配合と樸樕(ぼくそく=クヌギの樹皮)配合のものがあり、製薬会社によって実は生薬構成が異なっています。
桜皮エキスにはエストロゲン産生を促進する成分があることが確認されています。エストロゲンは女性ホルモンです。このため、皮膚表面においてエストロゲンが増えたほうが良い状況では桜皮を使っている十味敗毒湯のほうが有利に思えます。
私個人としては、女性の皮膚疾患では桜皮を含有する十味敗毒湯を選択することが多いです。
では樸樕を使用している十味敗毒湯には使い道がないのでしょうか?
男性の壮年性脱毛症(AGA)では、頭皮における悪玉テストステロンの活性が高まることで脱毛が促進されてしまうことが病態であると考えられています。ふつうのテストステロンを悪玉テストステロンに変換してしまう酵素が「5αリダクターゼ」という酵素で、この酵素には2つの型があります。
樸樕はAGAにおいて特に重要なⅠ型5αリダクターゼを阻害する働きがあります。
対して桜皮はⅠ型とⅡ型の両方を阻害する働きがあります。
そのため、余計なお世話ではあるのですがAGA傾向の男性の場合には樸樕を使用している十味敗毒湯を意識して選択しています。
樸樕は十味敗毒湯以外の漢方薬にも含まれています。
その1つが治打撲一方(じだぼくいっぽう)という漢方薬です。
AGAの治療を漢方薬だけで行うのはかなりの難題なのですが、男性の脱毛症のご相談をいただいた場合で、瘀血の兆候が目立つ患者様の場合には個人的には治打撲一方を駆瘀血剤(抹消血流改善)として使用しています。
桜皮と樸樕は漢方の古典には登場しない生薬なので、上記のように近年の成分分析の結果に基づいた使い分けをしています。
漢方薬の生薬1つにも数十種類の薬理成分が入っています。それらを丹念に細かく解析していき、主要な生薬の分析が出そろったところでビッグデータ解析をおこなうことで、漢方薬の新しい使い方や適応疾患が見つかっていくのではないかと期待に胸を膨らませている毎日です。
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆チャンネル登録よろしくおねがいします☆
YouTube ▶ https://www.youtube.com/channel/UCZ77mmHqYxWycSWBzpDRsxQ
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆チャンネル登録よろしくおねがいします☆
YouTube ▶ https://www.youtube.com/channel/UCZ77mmHqYxWycSWBzpDRsxQ
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪