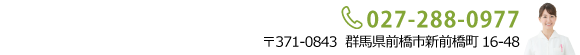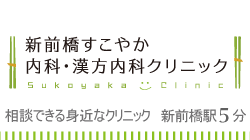作用と副作用について
2021/8/24「漢方薬は副作用がないんでしょう?」
漢方診療をしているとこのようなご質問をしばしば受けます。
漢方薬といえど、人体になんらかの作用を起こす薬理物質が含まれているのですから、好ましくない作用としての副作用は当然、起きる可能性があります。そうです。副作用というのは、起こるはずのない異常な事態ではなく、薬の作用機序から考えて当然起こりうる効果のうち、使用者にとって不都合な作用のことを言うのです。
ここで、薬の作用と副作用について一般の方が(一部の医療従事者も)誤解している点をお話してみようと思います。
ある薬(化学物質X)が人体に投与されると、なんらかの反応を起こすとします。
例えば血圧が下がるとか、痛みが鎮まるとか、よく眠れるとか。
物質Xが血圧を下げる効果を持っている理由は、人体が血圧を上昇させる複数の生化学的・生理反応的な経路のどこかに影響を持っているからです。一部の反応を進めるとか抑えるとか。
自動車にアクセルとブレーキがあるように、人体もアクセルとブレーキが備わっており、ほぼ全自動でバランスをとってくれています。その性質のことをホメオスタシス(恒常性)と言います。
話を本題に戻しましょう。
最後に、不都合な効果のはずの副作用が、実は非常に有益な(好都合な)作用だった例を一つ。
それはAGA(壮年性脱毛症)に使用されるフィナステリドです。
フィナステリドは前立腺肥大症の治療薬として見いだされ、開発されました。そして前立腺肥大症の臨床に使用が始まると、次々と不思議な副作用が報告されたのです。
それは「髪の毛が生えてきた!」という副作用でした。
「ハゲの特効薬を作れたらノーベル賞」と何十年も前から言われている医学界で、フィナステリドの副作用はまさしく多くの人に希望を与えた作用でした。そしてフィナステリドの副作用は、AGAに対する好ましい作用(効果・効能)となったのです。
漢方診療をしているとこのようなご質問をしばしば受けます。
漢方薬といえど、人体になんらかの作用を起こす薬理物質が含まれているのですから、好ましくない作用としての副作用は当然、起きる可能性があります。そうです。副作用というのは、起こるはずのない異常な事態ではなく、薬の作用機序から考えて当然起こりうる効果のうち、使用者にとって不都合な作用のことを言うのです。
ここで、薬の作用と副作用について一般の方が(一部の医療従事者も)誤解している点をお話してみようと思います。
ある薬(化学物質X)が人体に投与されると、なんらかの反応を起こすとします。
例えば血圧が下がるとか、痛みが鎮まるとか、よく眠れるとか。
物質Xが血圧を下げる効果を持っている理由は、人体が血圧を上昇させる複数の生化学的・生理反応的な経路のどこかに影響を持っているからです。一部の反応を進めるとか抑えるとか。
自動車にアクセルとブレーキがあるように、人体もアクセルとブレーキが備わっており、ほぼ全自動でバランスをとってくれています。その性質のことをホメオスタシス(恒常性)と言います。
アクセルとブレーキが自律神経、全自動運転機能がホメオスタシスですね。
さて、物質Xが人体の中で何らかの反応を起こすと、アクセルが強く踏み込まれて、結果として車が加速するとします。
そうすると車は急加速したりするわけで、車内に乗っている人は急加速の反動でヘッドレストに頭をぶつけてしまうかもしれません。手にジュースを持っていたらこぼしてしまうかも。アイスクリームを舐めていたら顔にべしゃっとぶつけてしまうかもしれませんね。
そんなわけでアクセルを急に踏むと車内でいろいろなトラブルが起きるわけですが、これが副作用なわけです。
さて、物質Xが人体の中で何らかの反応を起こすと、アクセルが強く踏み込まれて、結果として車が加速するとします。
そうすると車は急加速したりするわけで、車内に乗っている人は急加速の反動でヘッドレストに頭をぶつけてしまうかもしれません。手にジュースを持っていたらこぼしてしまうかも。アイスクリームを舐めていたら顔にべしゃっとぶつけてしまうかもしれませんね。
そんなわけでアクセルを急に踏むと車内でいろいろなトラブルが起きるわけですが、これが副作用なわけです。
全自動運転システム(ホメオスタシス)のほうは急加速を検知して、車体を制御するためにブレーキを作動させるわけです。
まぁ…いろいろなことが起きるというわけですね。
薬の作用と副作用も同じような関係です。
ある化学物質Xが持っている、期待される効果が「作用」と名付けられ、物質Xが持っている余計な効果(不都合な効果)が「副作用」と名付けられているのです。
でも人体にとってみてはどれもこれも起こるべくして起こっている現象なわけです。
薬の作用、副作用とはこのような話なわけで、期待される効果が不都合な効果にくらべて損得勘定で得が多いと考える場合にその薬が利用されているというわけです。
だから作用と副作用は一体なのだということです。
副作用は生じて当然。副作用が生じないのなら作用も生じないということになるわけで、それは薬としては何の役にもたたないということですね。
まぁ…いろいろなことが起きるというわけですね。
薬の作用と副作用も同じような関係です。
ある化学物質Xが持っている、期待される効果が「作用」と名付けられ、物質Xが持っている余計な効果(不都合な効果)が「副作用」と名付けられているのです。
でも人体にとってみてはどれもこれも起こるべくして起こっている現象なわけです。
薬の作用、副作用とはこのような話なわけで、期待される効果が不都合な効果にくらべて損得勘定で得が多いと考える場合にその薬が利用されているというわけです。
だから作用と副作用は一体なのだということです。
副作用は生じて当然。副作用が生じないのなら作用も生じないということになるわけで、それは薬としては何の役にもたたないということですね。
「クスリはリスク」とはよく言ったもので、医療行為には何らかの不都合な面(副作用とか後遺症とか合併症とか)があるわけですが、そのデメリットを超えるメリットがあるから正当化されるのです(死を免れるとか、日常生活の質を大幅に改善するとか)。
外科医が最初に肝に銘じることとして「手術という人傷つける行為が犯罪にならないのは、それが医療行為としてデメリットよりもメリットが大きく上回るから容認されるのだ」という教えがあります。
全くその通りなわけです。だから外科医という立場からは、むやみやたらに身体を傷つける行為をファッションや文化として受け入れることには抵抗を感じてしまいます。
話を本題に戻しましょう。
漢方薬に副作用がないのかと言えば当然あるわけです。
有名なものが偽アルドステロン症(低カリウム血症、高血圧、浮腫、脱力)や間質性肺炎、肝機能障害ですがこれらは甘草や柴胡、黄ゴンなどの生薬が起こしやすいことも知られています。
漢方薬が西洋薬と比べて副作用が少ないとイメージされる理由は、西洋薬が基本的に単一化学物質であるのに対して、漢方薬は複数の生薬を組み合わせてできあがっているという点にあります。
漢方薬は生薬の組み合わせによって、期待される効果は大きく、不都合な効果は小さく抑えることを狙って作成されています。その結果、西洋薬と比べると副作用が軽減されているのです。
有名なものが偽アルドステロン症(低カリウム血症、高血圧、浮腫、脱力)や間質性肺炎、肝機能障害ですがこれらは甘草や柴胡、黄ゴンなどの生薬が起こしやすいことも知られています。
漢方薬が西洋薬と比べて副作用が少ないとイメージされる理由は、西洋薬が基本的に単一化学物質であるのに対して、漢方薬は複数の生薬を組み合わせてできあがっているという点にあります。
漢方薬は生薬の組み合わせによって、期待される効果は大きく、不都合な効果は小さく抑えることを狙って作成されています。その結果、西洋薬と比べると副作用が軽減されているのです。
2000年を超える先人の知恵と努力と創意工夫の結果ですね。
最後に、不都合な効果のはずの副作用が、実は非常に有益な(好都合な)作用だった例を一つ。
それはAGA(壮年性脱毛症)に使用されるフィナステリドです。
フィナステリドは前立腺肥大症の治療薬として見いだされ、開発されました。そして前立腺肥大症の臨床に使用が始まると、次々と不思議な副作用が報告されたのです。
それは「髪の毛が生えてきた!」という副作用でした。
「ハゲの特効薬を作れたらノーベル賞」と何十年も前から言われている医学界で、フィナステリドの副作用はまさしく多くの人に希望を与えた作用でした。そしてフィナステリドの副作用は、AGAに対する好ましい作用(効果・効能)となったのです。
そういえば、「不都合な真実の不都合な真実」という面白い映画がむかしありました。
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪