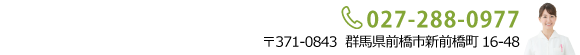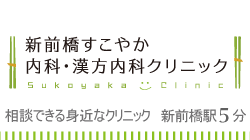夏やせ、夏まけ、暑気あたり・・・夏がニガテなあなたのための漢方薬
2021/6/25今年の関東地方は、梅雨入り後もまとまった雨が降らずに夏日が続いていますね。
暑い日が続くのでついつい冷たい飲み物ばかり飲んでしまい
食事も冷たい麺類ばかり食べてしまい
夜は寝苦しくて眠りが浅いし
外は暑いのに屋内は冷房がガンガン利いていて凍えるほど寒い…
気が付いたらなんだかだるくて毎日元気が出ない。
仕事も勉強もやる気が出ないしちょっと動くと息切れする。
いつの間にか食欲もなくなってきて、お腹は下痢気味…
体重まで減ってしまった…
こんなことになってしまっていませんか?
これはいわゆる夏やせ、夏まけ、暑気あたりと言われる状態です。
夏の暑さと環境の変化に体がついていけずに消耗してしまっている状態ですね。
昔は冷房などありませんでしたので、当然、こんな時に適した漢方薬が存在します。
清暑益気湯(せいしょえっきとう)という漢方薬です。名前が効果を表現していますね。
この漢方薬は補中益気湯(ほちゅうえっきとう)という、元気をつける有名な漢方薬の親戚のような漢方薬です。
元気をつける朝鮮人参と黄耆の他に、身体にうるおいを与える麦門冬や五味子が入っています。
夏の暑さのせいで体力を消耗し、胃腸が弱ってしまうため、水のめぐりに不調が生じているところに元気をもたらすとともに不足した部分にはうるおいを与えてくれるわけです。
夏のせいで消耗してしまい、疲労感、気力の減退、息切れ、食欲の減退、口やのどの渇き、尿量の減少、下痢などの症状に適しています。
夏専用の漢方薬のように思えますが「元気をつける」+「うるおいをもたらす」の2つの効果があるため、補中益気湯よりもこちらの方を好んで内服される患者さんもいらっしゃいます。そういう場合には一年中内服されます。
夏の漢方薬といえば熱中症の場合には白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)なわけですが、
清暑益気湯はなにをしたわけでもなくジリジリと夏の暑さで消耗していった結果の不調に使用します。
こうしてちゃんと処方があるのですから、昔の人も夏の暑さに苦しめられていたのですね。
理想はもちろん、清暑益気湯に頼らずに夏を乗り切ることです。
規則正しい生活のリズム、お腹を冷やさない食事、ほどほどの冷房などなど、工夫して元気に過ごしたいものですね。
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
☆メッセージも受け付けています☆
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪