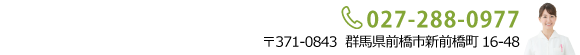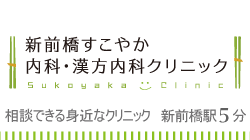リトリール療法とアンズのはなし
2021/5/11かつてアメリカを中心に「リトリール」という代替医療が一世を風靡したことがあります。
リトリールは杏子(あんず)のタネから抽出した成分であり、その成分であるアミグダリンは癌の特効薬としてビタミンB17の異名を取りました。
現在でもリトリールは癌に対する代替医療として利用されていますが、当然ながら大変な批判を浴び、主流医療からは排除されています。
私が調べた範囲では統計的な治療成績を見つけることはできませんでしたが、現在でもリトリール療法は続けられており、リトリール療法によるガンの寛解例も報告されてはいるため、効く人には効くのだろうと思います。
その話とはまったく別の筋の話なのですが、中国医学(中医学)の先生の漢方薬解説書を読んでいたところリトリールの効果を裏付ける内容を見つけました。
漢方薬で使用する生薬にも杏子の仲間が存在しますが、その中でも苦杏仁という生薬についての解説です。
苦杏仁にはアミグダリンという化学成分が3~4%含まれています。これが加水分解されると、ごく少量の青酸が発生します。微量の青酸は呼吸中枢を軽度抑制するため、咳や喘息を鎮める効果をもたらします(かつてサスペンスドラマではよく使用されましたね)。
また、苦杏仁を加水分解するとベンズアルデヒドも生じます。ベンズアルデヒドは胃のタンパク分解酵素を抑制するため、胃潰瘍に対する治療効果を発揮します。
さて、アミグダリンとベンズアルデヒドが登場しました。この両者も基礎実験では抗がん作用が確認されています。ラットに癌細胞を接種し、アミグダリンを投与した実験(癌の基礎研究では一般的な実験です)ではアミグダリンを投与されたラットの生存期間の延長が認められました(通常、すべてのラットが死亡するまで観察されるため、生存期間の延長で評価されます)。また、同様の実験でマウスに苦杏仁を自由に摂食させた場合でも癌細胞の成長を抑制し、生存期間が延長することが確認されました。
(このように基礎実験のレベルでガンに対する素晴らしい治療効果をもたらす物質は非常にたくさんあります。しかし、創薬段階にまで至る化学物質はほとんどありません。基礎実験と人体における効果とのあいだには非常に大きな隔たりがあるのです。)
癌細胞では、青酸を解毒するローダナーゼという酵素活性が正常細胞よりも少ないため苦杏仁が抗癌効果を発揮するのだと言います。
このように、リトリール(ビタミンB17)の抗がん作用がまったく別のところで証明されたわけではあるのですが、しかし苦杏仁の多量摂取はやはり青酸中毒を起こすため勧められることではありません。中医学の先生のあいだでも意見が分かれているようです。
ただ、これらの知見は抗癌剤開発研究にとって重要なインスピレーションをもたらすのではないかと思われますし、日頃から杏子類を適量摂取することで(杏仁豆腐など)、体内における癌の発生や進展を抑制できるのかもしれません。希望的観測に過ぎませんが。
しかし、日本の漢方でもこのような生薬研究が進むことが期待されますね。
リトリールは杏子(あんず)のタネから抽出した成分であり、その成分であるアミグダリンは癌の特効薬としてビタミンB17の異名を取りました。
現在でもリトリールは癌に対する代替医療として利用されていますが、当然ながら大変な批判を浴び、主流医療からは排除されています。
私が調べた範囲では統計的な治療成績を見つけることはできませんでしたが、現在でもリトリール療法は続けられており、リトリール療法によるガンの寛解例も報告されてはいるため、効く人には効くのだろうと思います。
その話とはまったく別の筋の話なのですが、中国医学(中医学)の先生の漢方薬解説書を読んでいたところリトリールの効果を裏付ける内容を見つけました。
漢方薬で使用する生薬にも杏子の仲間が存在しますが、その中でも苦杏仁という生薬についての解説です。
苦杏仁にはアミグダリンという化学成分が3~4%含まれています。これが加水分解されると、ごく少量の青酸が発生します。微量の青酸は呼吸中枢を軽度抑制するため、咳や喘息を鎮める効果をもたらします(かつてサスペンスドラマではよく使用されましたね)。
また、苦杏仁を加水分解するとベンズアルデヒドも生じます。ベンズアルデヒドは胃のタンパク分解酵素を抑制するため、胃潰瘍に対する治療効果を発揮します。
さて、アミグダリンとベンズアルデヒドが登場しました。この両者も基礎実験では抗がん作用が確認されています。ラットに癌細胞を接種し、アミグダリンを投与した実験(癌の基礎研究では一般的な実験です)ではアミグダリンを投与されたラットの生存期間の延長が認められました(通常、すべてのラットが死亡するまで観察されるため、生存期間の延長で評価されます)。また、同様の実験でマウスに苦杏仁を自由に摂食させた場合でも癌細胞の成長を抑制し、生存期間が延長することが確認されました。
(このように基礎実験のレベルでガンに対する素晴らしい治療効果をもたらす物質は非常にたくさんあります。しかし、創薬段階にまで至る化学物質はほとんどありません。基礎実験と人体における効果とのあいだには非常に大きな隔たりがあるのです。)
癌細胞では、青酸を解毒するローダナーゼという酵素活性が正常細胞よりも少ないため苦杏仁が抗癌効果を発揮するのだと言います。
このように、リトリール(ビタミンB17)の抗がん作用がまったく別のところで証明されたわけではあるのですが、しかし苦杏仁の多量摂取はやはり青酸中毒を起こすため勧められることではありません。中医学の先生のあいだでも意見が分かれているようです。
ただ、これらの知見は抗癌剤開発研究にとって重要なインスピレーションをもたらすのではないかと思われますし、日頃から杏子類を適量摂取することで(杏仁豆腐など)、体内における癌の発生や進展を抑制できるのかもしれません。希望的観測に過ぎませんが。
しかし、日本の漢方でもこのような生薬研究が進むことが期待されますね。
現代はビッグデータの時代ですから、生薬に含まれる何十もの化学成分の相乗効果や相互作用などを多元的に解析できると漢方薬の真の効果や新たな使い道が発見できるように思います。
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
いつの日も こころ楽しく すこやかに
⇩⇩⇩こちらもチェック♪⇩⇩⇩
【新前橋すこやか内科・漢方内科クリニックSNS】
☆クリニックの日常風景やお知らせはこちらで☆
Instagram ▶ sukoyakanaika / sukoyaka_harusan / sukoyakastaff
Facebook ▶ 新前橋すこやか内科・漢方内科クリニック
☆ショップカードを作ってイベント参加しよう!☆
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪
公式LINEアカウント ▶ @sukoyakaclinic または https://lin.ee/EvFfL7C
♪LINEから受診予約やお問い合わせができます♪